こんばんは!
親子のコミュニケーションをスムーズにして、子どもの成長を加速させる【くま先生】です。
今日は、ちょっとした工夫で大きく変わる「癇癪」についてお話ししようと思います。
最近、あるお母さんからこんな相談を受けました。「子どもがちょっとしたことで癇癪を起こして、どう対処したらいいか分からない」とのこと。
その日は、A君(5歳)の朝の準備がスムーズにいかず、意図せず癇癪を起こしてしまいました。朝食のトーストが焼きすぎたことが原因でした。いつもと違う焦げた音に驚いて泣き出したA君。お母さんは、すぐに「大丈夫よ」と言ったものの、A君はますますパニックに。そこで、ちょっとした工夫を試みました。お母さんは、まずA君の目の高さにしゃがみ、「焦げてしまったトースト、どうする?」と一緒に考えてみることにしたのです。すると、A君は「新しいのを焼こう!」と少し冷静になり、無事にごはんを食べることができました。
癇癪はなぜ起こる?
癇癪が起こる原因は、実は様々です。特に、発達グレーゾーンの子どもたちは、感覚過敏や環境の変化に敏感であることが多いです。A君の場合、朝の準備の中で普段と違うことが起きたために、彼の不安が募り、癇癪につながりました。こうした状況を理解し、親も無理に抑え込もうとするのではなく、一緒に対処する姿勢が重要です。
さて、ここで親子のコミュニケーションのコツですが、まずは「共感」を大切にしましょう。「どうしてそんなに怒っているの?」「何が嫌だったの?」と問いかけることで、子どもは自分の気持ちを言葉で表現する訓練にもなります。A君のお母さんのように、子どもの目線に立って話すことが、信頼関係を築く第一歩です。
癇癪と向き合うコミュニケーションのコツ
次に、癇癪を和らげるための具体的な方法ですが、「朝の癇癪編」として、まずは環境を整えることから始めましょう。朝の時間は慌ただしいですが、少し落ち着いた雰囲気を作るために、朝食を準備する際に音を立てすぎないようにしたり、子どもが好きな音楽を流すことも効果的です。
最後に、親としてどう向き合うべきかを考えると、子どもが癇癪を起こした時には、まずは冷静になり、心の中で「子どもは今、何を感じているのだろう?」と問いかけてみてください。お母さん、お父さんが悪いわけではありません。ちょっとしたコミュニケーションのコツをつかむことが、子どもの成長をサポートする大きな力になりますよ。
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしくださいね!
#癇癪 #コミュニケーション #共感
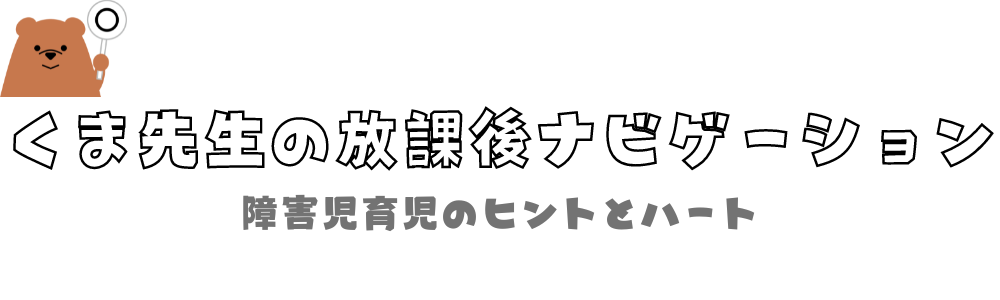
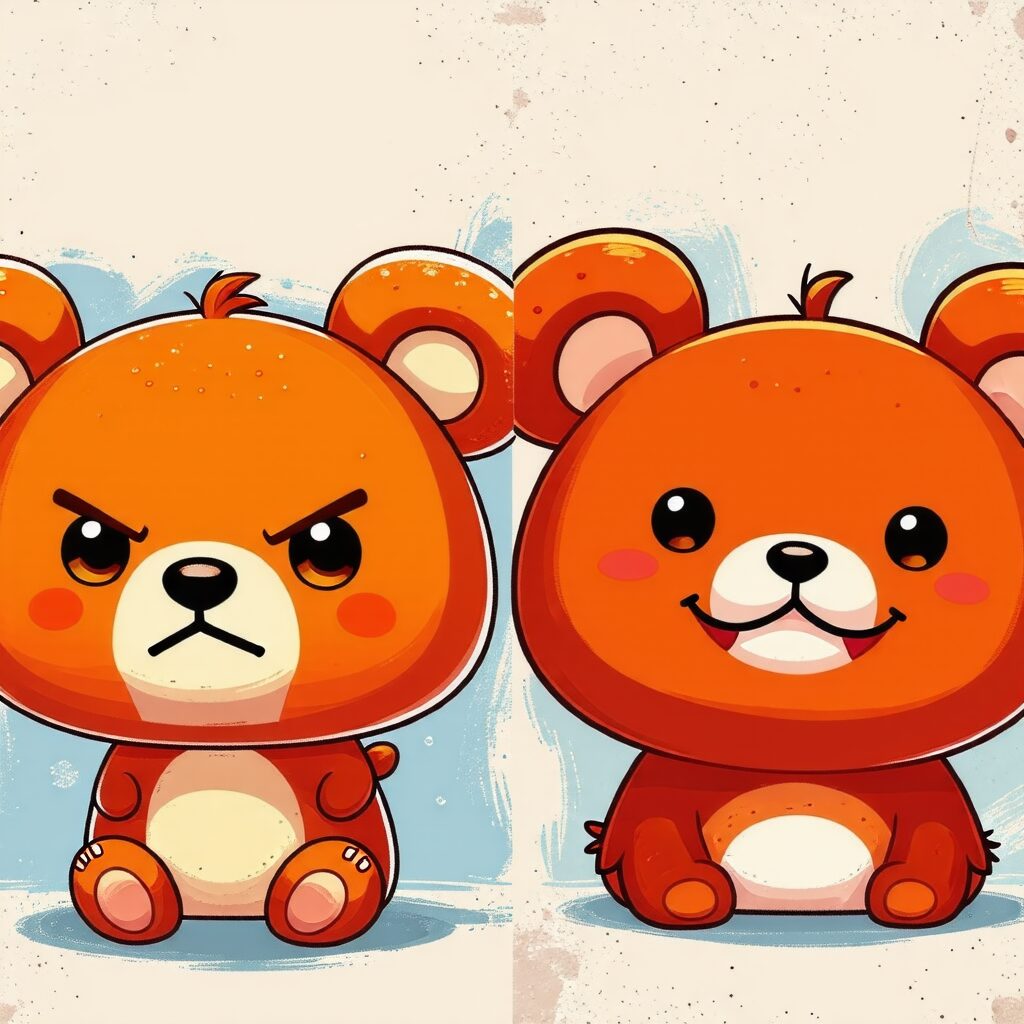
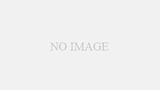

コメント