みなさん、おはようございます!
ぬくぬくコミュニケーションのくま先生です。
先日、放課後デイサービスで心温まる出来事がありました。ハナちゃん(6歳、ADHD)が、いつものように落ち着きなく動き回っていました。お絵かきの時間なのに、筆を持つ手が止まらず、紙の上をグルグル。お母さんが「ハナ、ちゃんと絵を描きなさい」と言っても、ハナちゃんはますます落ち着かなくなってしまいました。そこで私は、ハナちゃんの隣に座って、「ハナちゃん、その線とってもダイナミックだね。何を描いているの?」と聞いてみました。すると、ハナちゃんは嬉しそうに「台風だよ!強い風がグルグル回ってるの」と答えてくれたんです。
これこそが「共感」の力なんですね。特性を持つお子さんとのコミュニケーションで、最も大切なのは「共感してあげること」なんです。
実は、脳科学の研究で興味深いことがわかっています。ADHDのお子さんは、前頭前野という脳の部位の活動が少し弱いことがあるんです。この部位は注意力や衝動性のコントロールに関わっています。だから、じっとしていられなかったり、集中が続かなかったりするんですね。でも、ハナちゃんの場合、その「落ち着きのなさ」が創造性につながっていたんです。私たちが「台風」と共感することで、ハナちゃんの行動が「問題」ではなく「表現」として認められたんですね。

ちょっとした工夫で、大きく変わります。お子さんの行動を否定的に見るのではなく、「どんな気持ちでそうしているのかな?」と考えてみてください。そして、その気持ちに寄り添って言葉をかけてみてください。周りの大人たちのちょっとしたコミュニケーションのコツで、子どもたちは大きく変わっていきます。共感の気持ちを持って接すると、お子さんの心が開いていくのを感じられると思います。
最後に、ハナちゃんの話の続きです。私が台風の話を聞いていると、他の子どもたちも興味を持ち始めました。「僕は雨を描く!」「私は風で飛ぶ葉っぱを描きたい!」と声が上がり、自然と台風をテーマにした共同制作が始まったんです。共感の力って、本当にすごいですね。みなさんも、ぜひ試してみてください。くまのように大きな心で、お子さんの世界に寄り添ってあげてくださいね。
#共感 #寄り添う #表現
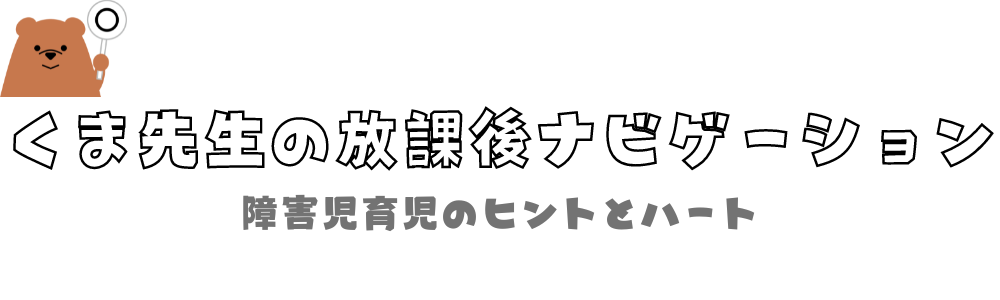



コメント