おはようございます!
ぬくぬくコミュニケーションのくま先生です。みなさん、お元気ですか?
先日、放課後デイサービスで印象的な出来事がありました。5年生の太郎くん(仮名)が、算数のテストの結果を見て、「僕はバカだ。もう勉強なんてしたくない」と泣き出してしまったんです。太郎くんのお母さんは、「頑張ったんだから、次は大丈夫よ」と励ましていましたが、太郎くんの気持ちは晴れませんでした。
この場面を見て、私は「ネガティブになりやすい子ども」へのコミュニケーションの大切さを改めて感じました。今日は、そんな子どもたちとのコミュニケーションの工夫について、お話ししたいと思います。
まず、大切なのは子どもの気持ちを受け止めることです。「バカじゃないわよ」と否定するのではなく、「テストの結果を見て悲しくなったんだね」と共感することから始めましょう。これは、子どもの脳の扁桃体(へんとうたい)を落ち着かせる効果があります。扁桃体は感情を司る部分で、ストレスを感じると過剰に反応してしまいます。共感的な言葉かけは、この反応を和らげるんです。
次に、具体的な行動を提案してみましょう。「次は頑張ろう」という抽象的な言葉ではなく、「苦手な問題を3つ一緒に解いてみようか」といった具体的な提案です。これは、前頭前野の実行機能を刺激します。実行機能は計画立案や問題解決に関わる能力で、具体的な目標設定によって活性化されるんです。
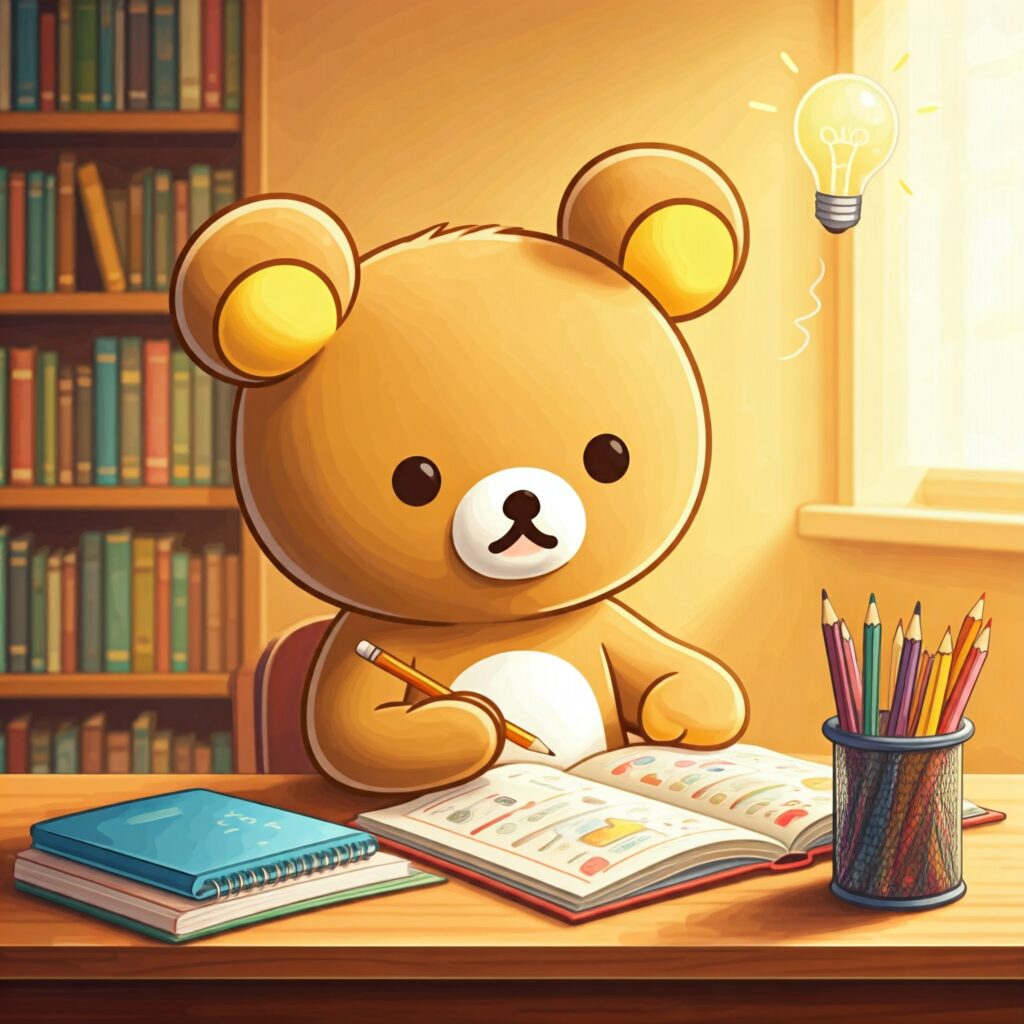
そして、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。「この問題が解けたね!すごい!」と、一つ一つの達成を認めていきましょう。これは、脳内の報酬系を刺激し、ドーパミンの分泌を促します。ドーパミンは「やる気」や「達成感」に関わる神経伝達物質で、学習意欲の向上につながります。
昨日も、太郎くんと一緒に算数の問題を解いてみました。最初は嫌がっていましたが、「まずは1問だけやってみようか」と提案すると、少し気が楽になったようでした。1問解けると、「もう1問チャレンジしてみる?」と声をかけ、少しずつ問題数を増やしていきました。最後には、「先生、もっとやりたい!」と言ってくれたんです。
この経験から、ネガティブな気持ちを和らげるには、子どもの脳の特性を理解し、それに合わせたコミュニケーションが効果的だと実感しました。
ちょっとしたコミュニケーションの工夫で、子どもたちの気持ちは大きく変わるんです。子どもの気持ちを受け止め、具体的な行動を提案し、小さな成功体験を積み重ねる。この3つのポイントを意識してみてください。
最後に、くまさんからのアドバイスです。子どもたちは一人ひとり違います。同じ方法が全ての子どもに効果的とは限りません。でも、大切なのは諦めないこと。子どもたちの可能性を信じて、一緩に寄り添っていきましょう。きっと、素敵な変化が待っていますよ。
みなさんの子育てに、幸あれ!くま先生でした。
ご感想・ご相談はお気軽に♪
みなさん、いかがでしたか?このコラムを読んで、新しい発見や気づきはありましたか?くま先生は、みなさんのお子さんについての悩みや質問、そしてこのコラムへの感想をお待ちしています。「うちの子、こんな時どうしたらいいの?」
「この方法、うちの子にも効果があるかな?」
「コラムを読んで、こんなことを試してみたよ!」など、どんな些細なことでも構いません。みなさんの声を聞かせてください。一緒に、お子さんの輝く未来を育んでいきましょう。
ご質問やご感想は、コメント欄またはお問い合わせフォームからお寄せください。くま先生が心を込めて、一つ一つ丁寧にお返事させていただきます。お子さんの成長を一緒に喜び合えることを楽しみにしています。さあ、みなさんの声をお聞かせください。くま先生は、あなたとあなたのお子さんを全力でサポートします!
#勉強 #特性 #報酬系
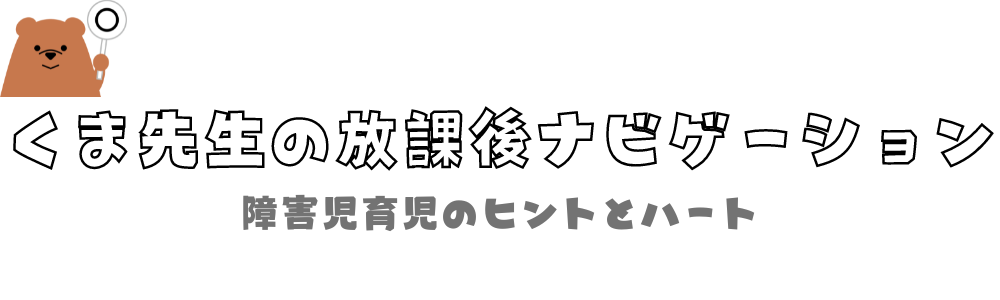
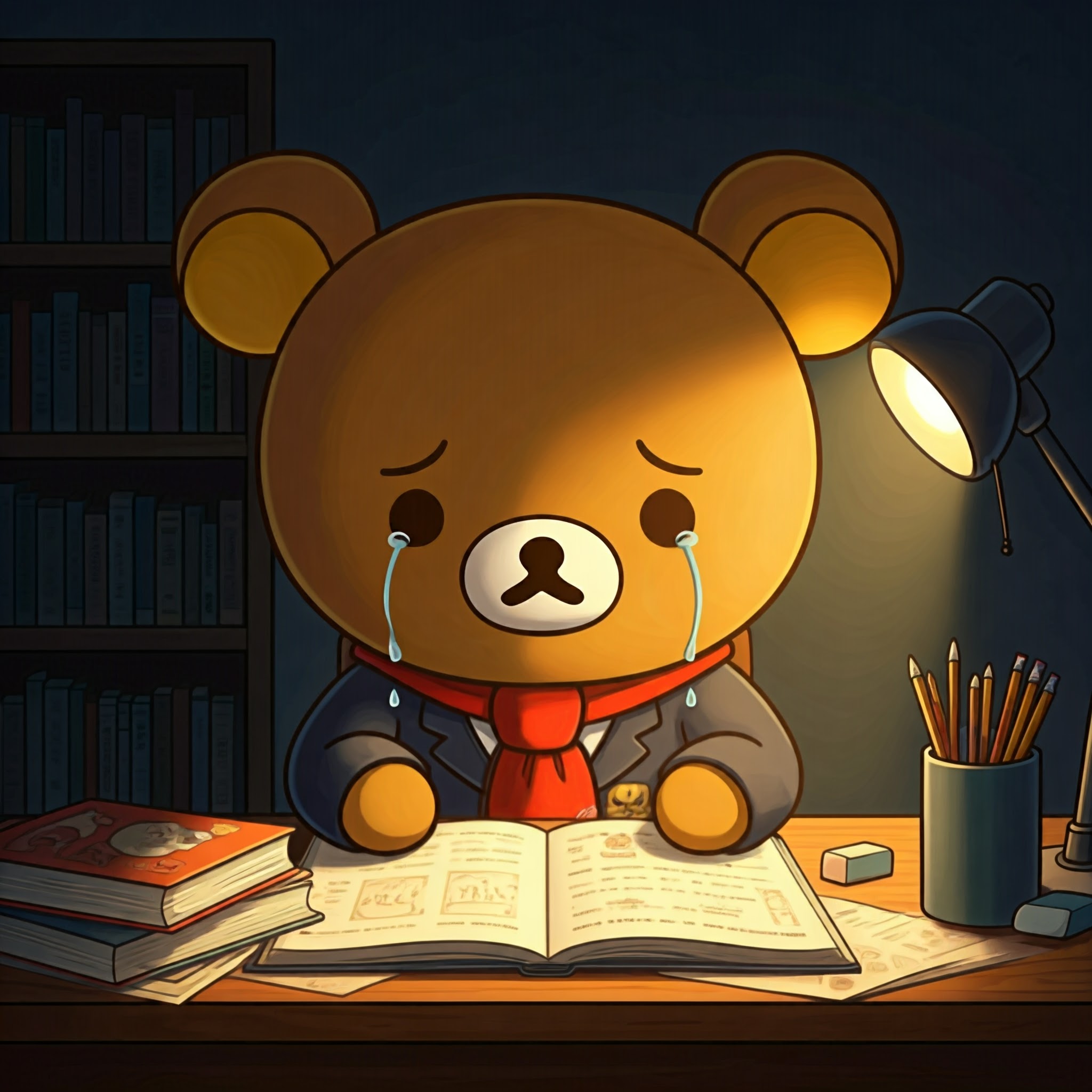


コメント