おはようございます!
ぬくぬくコミュニケーションのくま先生です。みなさん、お元気ですか?
昨日、放課後デイサービスでちょっと面白いことがありました(^^)/
ADHDのケンジくん(仮名)が、いつものように落ち着きなく動き回っていたんで「ケンジくん、ちょっと座ってお話しようか」と声をかけたら、「えー、嫌だよ」って言われちゃいました。でも、ここからが面白いんですよ。
「ケンジくん、今日の朝ごはん何食べた?」って聞いたら、ピタッと止まって「えっと…トースト!」って答えてくれたんです。そこから、トーストの話で盛り上がって、気づいたら10分も座って話せたんですよ。
これって、ちょっとしたコミュニケーションの工夫で、ADHDの子どもたちの気持ちをそらさず、会話を続けられるってことなんです。今日は、そんな「ADHDの気持ちをそらさない声かけ」についてお話ししますね。
まず、ADHDの子どもたちの脳の特徴について、ちょっと難しい話をしますよ。ADHDの子どもたちは、前頭前野という脳の部分の働きが少し弱いんです。この部分は、注意力や衝動性のコントロールに関わっているんですね。
だから、ADHDの子どもたちは、興味のないことにはすぐに飽きちゃうけど、逆に興味のあることには集中力がグッと高まるんです。これを「過集中」って言うんですよ。

この特徴を理解して、コミュニケーションを工夫すると、驚くほど会話が続くんです。例えば、「宿題やろうね」じゃなくて、「今日の算数の問題、恐竜の絵が描いてあったよね。あれ、何の恐竜だったっけ?」って聞いてみるんです。
すると、恐竜が好きな子なら、「ティラノサウルス!」って答えてくれて、そこから恐竜の話で盛り上がりながら、自然と宿題に取り組めちゃうんです。これって、脳の報酬系を上手に刺激して、やる気を引き出しているんですよ。
先日も、片付けが苦手なサクラちゃん(仮名)に、「お片付けゲームしよう!赤いおもちゃを見つけた人が勝ち!」って声をかけたら、あっという間に片付けが終わっちゃいました。これも、ゲーム感覚で楽しく取り組めるようにした工夫なんです。
大切なのは、子どもたちの興味や好きなことを知ること。そして、それを日常の活動に上手に組み込んでいくことなんです。
最後に、もう一つ大事なことをお伝えしますね。ADHDの子どもたちは、失敗経験が多いせいで、自己肯定感が低くなりがちなんです。だから、小さな成功体験を積み重ねることがとても大切。
「さっきの片付け、すごく上手だったね!」「宿題、集中して頑張ったね!」って、具体的に褒めてあげることで、子どもたちの自信につながるんです。
みなさん、ちょっとした工夫で、ADHDの子どもたちとのコミュニケーションはグッと楽しくなりますよ。今日からでも、お子さんの興味に合わせた声かけを試してみてくださいね。きっと、新しい発見があるはずです。
くま先生からの温かいハグをみなさんに送ります。また会いましょうね!
くま先生からのお願い
みなさん、くま先生のコラムはいかがでしたか?
お子さんとのコミュニケーションで「あっ、これ使えそう!」と思ったことはありましたか?
くま先生は、みなさんのお悩みやご質問をいつでもお待ちしています。「うちの子、こんな時どうしたらいいの?」「この方法、うまくいかないんだけど…」など、どんな小さなことでも構いません。
みなさんの声を聞かせてください。一緒に、お子さんとの素敵な関係づくりを考えていきましょう。
次回のコラムでは、みなさんからいただいたお悩みにお答えできるかもしれませんよ。くま先生からの温かいハグと共に、また会える日を楽しみにしています!
コラムへのご感想・ご相談はお問合せからお願いします!
#過集中 #自己肯定感 #興味
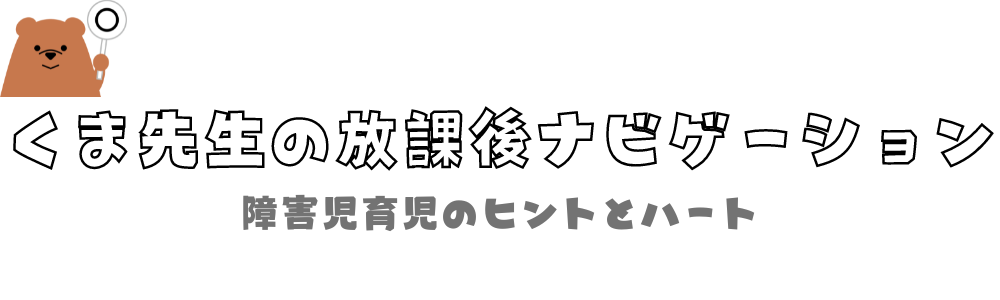
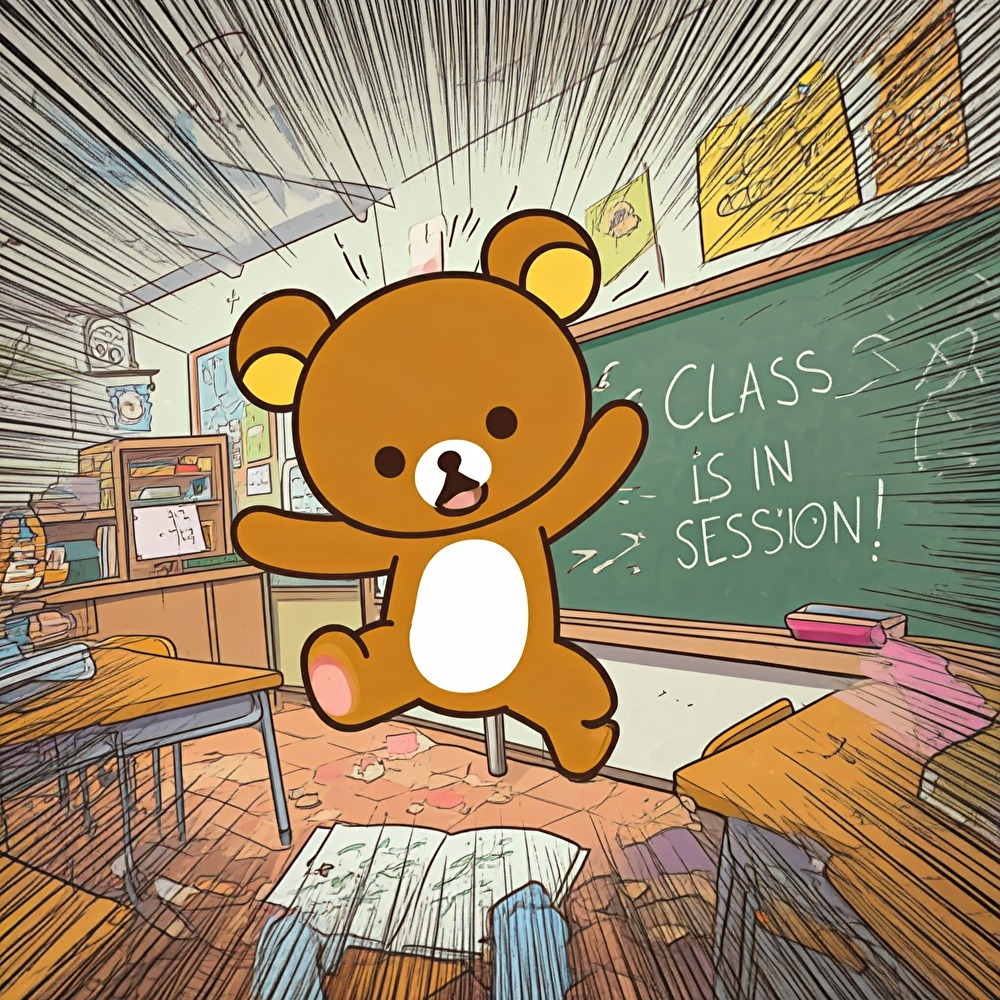


コメント