おはようございます!
ぬくぬくコミュニケーションのくま先生です。
昨日、放課後デイサービスでちょっとした出来事がありました。カンナちゃん(仮名)が、おもちゃの片付けをしようとしないんです。「カンナちゃん、おもちゃを片付けようね」と何度も声をかけましたが、まるで聞こえていないかのように遊び続けていました。
でも、ちょっとした工夫で状況が大きく変わったんです。その工夫とは何だったのか、今日はみなさんにお話ししたいと思います。
特性を持つお子さんに「すぐに動いてもらえる指示の出し方」について、一緒に考えてみましょう。
まず、大切なのは「コミュニケーションの工夫」です。特に、CCQ(Calm、Close、Quiet)というアプローチが効果的なんですよ。
Calm(おだやかに):まず、私自身が落ち着いた状態でタロウくんに接しました。おだやかな態度と声のトーンで話しかけると、タロウくんも安心して耳を傾けてくれるようになりました。
Close(近づいて):次に、タロウくんの近くまで行って、目線を合わせました。特に注意が散漫になりやすいお子さんには、この「近づく」というアクションが効果的なんです。
Quiet(静かに):最後に、周りの音を少し小さくして、シンプルで明確な言葉で指示を出しました。「タロウくん、赤いおもちゃを箱に入れようね」と、具体的に伝えたんです。

この3つのポイントを意識するだけで、タロウくんはすぐに動き出してくれました。驚きましたか?実は、この背景には科学的な根拠があるんです。
発達障害のあるお子さんの中には、感覚処理の特性があることがあります。例えば、周りの音や光に敏感だったり、逆に鈍感だったりすることがあるんです。だから、「Quiet」な環境を作ることで、お子さんが指示に集中しやすくなるんですね。
また、「Close」で近づくことは、視覚的な情報処理を助けます。ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんの中には、非言語的コミュニケーションが苦手な方もいます。だから、近づいて目線を合わせることで、言葉以外の情報もしっかり伝わりやすくなるんです。
そして「Calm」な態度は、お子さんの安心感につながります。脳科学的には、穏やかな環境下では扁桃体の活動が抑えられ、前頭前野の活動が活発になります。これにより、お子さんは落ち着いて指示を理解し、行動に移しやすくなるんです。
さらに、指示を出すときは一度に一つずつ、明確に伝えることが大切です。複数の指示を同時に出すと、情報処理に時間がかかってしまうお子さんもいるからです。
先日も、サクラちゃん(仮名)に「おもちゃを片付けて、手を洗って、おやつの準備をしてね」と言ったら、どうしていいか分からなくなってしまいました。でも「まず、おもちゃを箱に入れようね」と一つずつ伝えたら、スムーズに行動できたんです。
このように、ちょっとしたコミュニケーションのコツをつかむだけで、お子さんとの関わり方が大きく変わります。特性を持つお子さんの認知機能の特徴を理解し、それに合わせたアプローチをすることで、お子さんの可能性を最大限に引き出すことができるんです。
みなさんも、ぜひ試してみてくださいね。お子さんの「できた!」という笑顔が、きっと増えていくはずです。一緒に、お子さんの成長を見守っていきましょう。
くま先生からの温かいハグをお送りします。また会いましょう!
ご感想・ご相談をお待ちしております(^^)/
みなさん、いかがでしたか?
このコラムを読んで、新しい発見はありましたか?くま先生は、みなさんのお子さんの成長を心から応援しています。日々の子育ての中で感じる喜びや悩み、このコラムを読んでの感想など、どんなことでもお聞かせください。
特性を持つお子さんの子育てについて、もっと詳しく知りたいことや具体的な相談があれば、ぜひお寄せください。くま先生と一緒に、お子さんの笑顔を増やしていきましょう。
みなさんからのメッセージ、心よりお待ちしています!
#すぐ動く #CCQ #引き出す
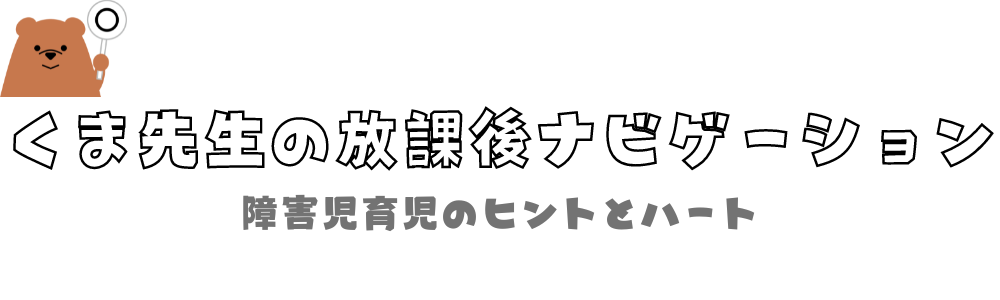



コメント