みなさん、おはようございます!
ぬくぬくコミュニケーションのくま先生です。
昨日、放課後デイサービスで面白いことがありました。小学3年生のゆうくんが、友達のはなちゃんに「あのね、はなちゃんの髪型、おばあちゃんみたい」って言ったんです。はなちゃんは泣いちゃって、ゆうくんは「なんで泣くの?」って困惑していました。
こういう場面、よくありますよね。「グレーゾーン」と呼ばれる子どもたちの中には、このようなコミュニケーションの難しさを抱えている子が多いんです。でも、「これも個性だから」「もう少し様子を見よう」って思っちゃうのは、実はよくないんです。なぜかというと、脳の発達には「臨界期」があるからなんです。
脳科学の研究によると、人間の脳には「臨界期」という、特定の機能が急速に発達する時期があります。特に、社会性やコミュニケーション能力の発達には、幼児期から学童期にかけての経験が重要なんです。この時期に適切な支援や経験が不足すると、後から取り戻すのが難しくなってしまうんです。
でも、安心してください。ちょっとした工夫で、子どもたちのコミュニケーション能力は大きく変わるんです。例えば、ゆうくんの場合、「相手の気持ちを考えて話す」というスキルを身につける必要がありました。そこで、私たちは「気持ちカード」というものを使って練習しました。
「気持ちカード」は、様々な表情が描かれたカードです。ゆうくんに「もし自分が『おばあちゃんみたい』って言われたら、どの表情になる?」って聞いてみたんです。ゆうくんは「悲しい顔」のカードを選びました。そこから、「じゃあ、どうすれば相手が喜ぶかな?」って一緒に考えました。
この方法は、実は脳の「ミラーニューロン」という部分を刺激するんです。ミラーニューロンは、他人の行動や感情を理解し、共感する能力に関わっています。「気持ちカード」を使うことで、ミラーニューロンが活性化され、相手の気持ちを想像する力が育つんです。

先日、ゆうくんが「はなちゃん、今日の髪型かわいいね」って言えたんです。はなちゃんがニコッと笑った瞬間、ゆうくんの目が輝いていました。きっと、「相手を喜ばせる」という経験が、ゆうくんの脳に新しい回路を作ったんだと思います。
みなさん、子どもたちの「困った行動」は、実は「助けて」というサインなんです。「様子を見よう」ではなく、「今、どんな支援ができるかな」って考えてみてください。ちょっとしたコミュニケーションのコツをつかむことで、子どもたちの世界はグッと広がります。
最後に、大切なのは「継続」です。脳の可塑性(かそせい)は、繰り返しの経験によって高まります。毎日の小さな積み重ねが、子どもたちの未来を明るくするんです。一緒に、子どもたちの可能性を広げていきましょう。くまさんも、みなさんと一緒に頑張ります!
くま先生からのお願い
みなさん、いかがでしたか?くま先生のお話を聞いて、何か新しい発見はありましたか?
お子さんのことで気になることや、悩んでいることがあれば、ぜひくま先生に相談してみてください。一人で抱え込まずに、一緒に考えていきましょう。
「うちの子、こんな行動をするんだけど…」
「コミュニケーションで困っていて…」
「発達のことで心配で…」
どんな小さなことでも構いません。くま先生が、みなさんの疑問や不安に、優しく丁寧にお答えします。
ご相談は「お問合せ」のフォームから受け付けています。くま先生からの温かいアドバイスが、きっとお子さんとの関わり方のヒントになるはずです。
一緒に、お子さんの輝く未来を作っていきましょう!
くま先生は、いつでもみなさんの味方です。
#臨界期 #可塑性 #ミラーニューロン
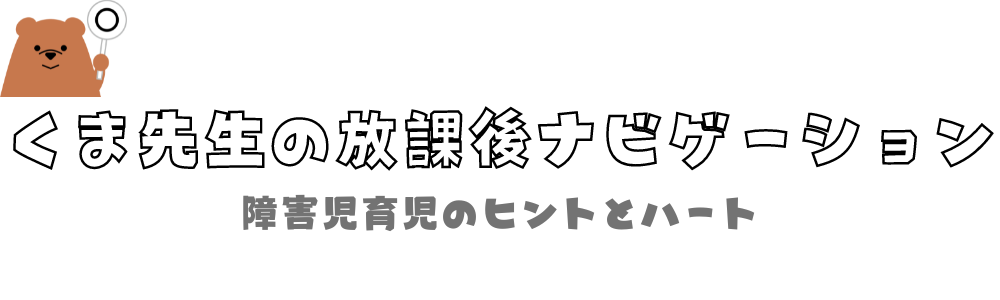



コメント