おはようございます!
ぬくぬくコミュニケーションのくま先生です。
昨日、放課後デイサービスでこんなことがありました。いつもはゲームに夢中なAくんが、突然「先生、冬休みの宿題どうしよう」と真剣な顔で聞いてきたんです。そこで、集団SSTの支援で冬休みの過ごし方について話し合ってみました。
さて、皆さんのお子さんは冬休みをどう過ごしていますか?宿題はちゃんとやっていますか?それとも、ゲームや動画ばかり見て、パジャマでゴロゴロしていませんか?長期休暇は楽しいものですが、特性を持つお子さんにとっては、日常のリズムが崩れやすく、困難を感じることもあるんです。
でも、大丈夫。ちょっとした工夫で、お子さんの冬休みを楽しく、そして有意義なものにできるんです。その秘訣は、コミュニケーションにあります。
まず、お子さんの認知特性を理解することが大切です。例えば、ASDのお子さんは視覚的な情報処理が得意な場合が多いんです。これは、脳の情報処理の仕方が関係しています。視覚野と呼ばれる脳の部位が、通常よりも活発に働いているんですね。
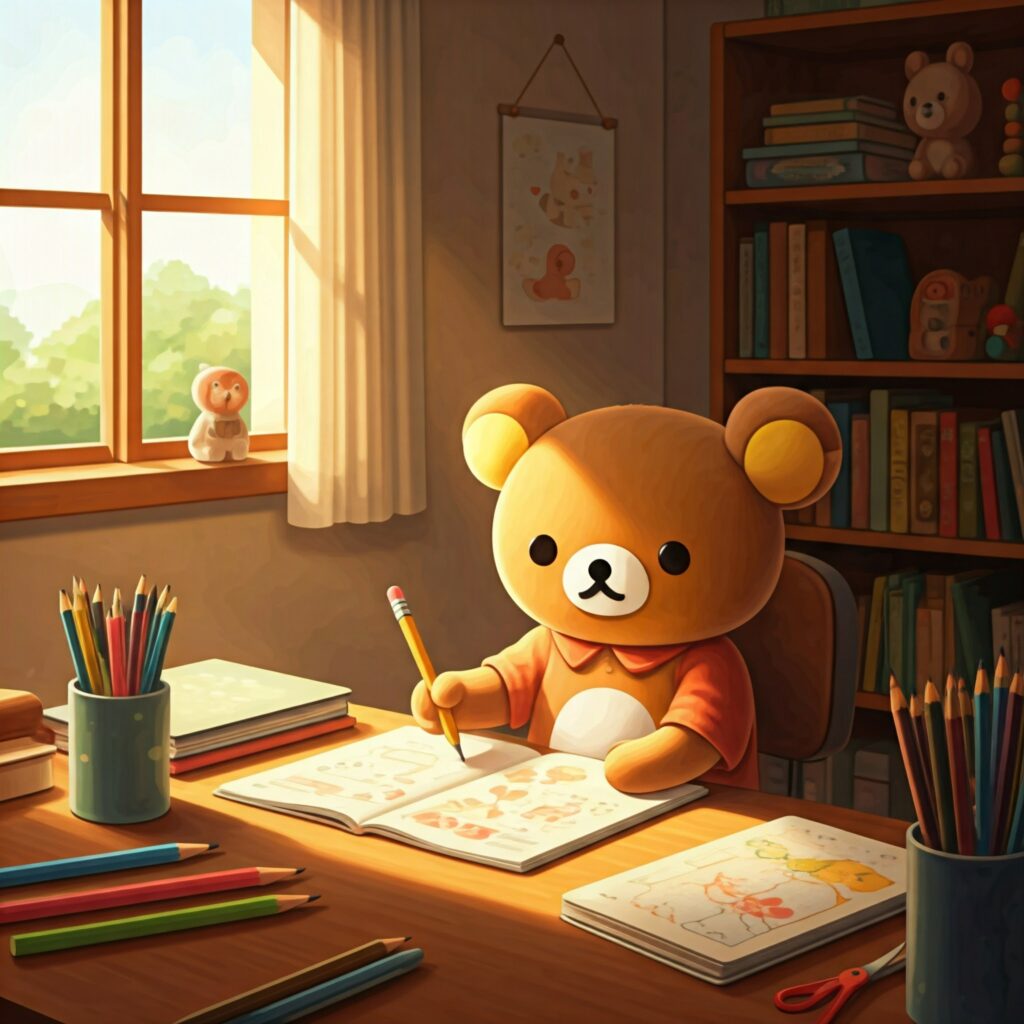
この特性を活かして、冬休みの予定を視覚化してみましょう。カレンダーや時間割を作って、宿題や遊びの時間を色分けして示すのです。「9時から11時は宿題タイム」「午後3時からはゲームOK」といった具合に。これだけで、お子さんは1日の流れを理解しやすくなります。
ADHDのお子さんの場合は、時間の感覚が曖昧になりがちです。これは、前頭前野という脳の部位が関係しています。時間管理や計画立てが苦手なんですね。そこで、タイマーを使って時間を可視化するのがおすすめです。「30分勉強したら、10分休憩」といったように、短い時間で区切ってみましょう。
また、達成感を味わえるような工夫も大切です。脳内の報酬系が活性化すると、やる気が出るんです。宿題を小さなタスクに分けて、1つ終わるごとにシールを貼るなど、小さな成功体験を積み重ねていくのがいいでしょう。
そして何より大切なのは、お子さんとのコミュニケーションです。「今日は何をして遊びたい?」「宿題で困っていることはある?」など、お子さんの気持ちに寄り添う会話を心がけましょう。これは、お子さんの前頭前野を刺激し、自己調整力を育むことにつながります。
先日、ある保護者の方から嬉しい報告がありました。視覚的なスケジュール表を導入したところ、お子さんが自主的に宿題に取り組むようになったそうです。「宿題が終わったら、好きな動画を見ていいよ」という約束も効果的だったとか。
皆さん、ちょっとしたコミュニケーションの工夫で、お子さんの冬休みは大きく変わるんです。お子さんの特性を理解し、それに合わせた環境づくりをすることで、楽しく充実した冬休みを過ごせるはずです。
最後に、くれぐれも無理をしないでくださいね。完璧を求めすぎると、かえってストレスになってしまいます。お子さんのペースを尊重しながら、少しずつ良い習慣を作っていけばいいんです。
さあ、みんなで楽しい冬休みを過ごしましょう!くま先生からの応援、忘れずに。
くま先生からのメッセージ
みなさん、いかがでしたか?このコラムを読んで、お子さんの冬休みの過ごし方について新しい発見はありましたか?
特性を持つお子さんの子育ては、時に大変なこともあるかもしれません。でも、ちょっとした工夫で、お子さんとの時間がもっと楽しく、もっと充実したものになるんです。
くま先生は、みなさんの悩みや疑問に寄り添いたいと思っています。「うちの子、こんな特徴があるんだけど、どうしたらいいかな?」「この方法を試してみたけど、うまくいかなくて…」など、どんな小さなことでも構いません。ぜひ、みなさんの体験や感想、質問をお聞かせください。一緒に考え、より良い方法を見つけていきましょう。
くま先生は、いつでもみなさんの味方です。お子さんの笑顔のために、一緒に頑張りましょうね!
#冬休み #可視化 #自己調整力
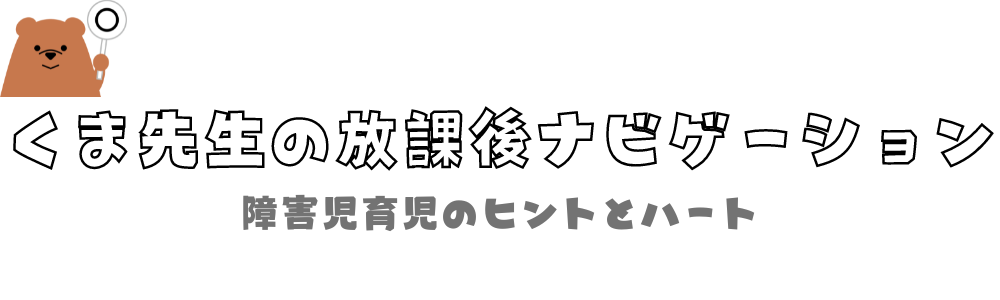



コメント