おはようございます!
ぬくぬくコミュニケーションのくま先生です。
今日は、特性を持つお子さんへの褒め方についてお話しします。
昨日、放課後デイサービスでこんなことがありました。タロウ君(仮名)が、みんなの前でお絵かきを上手に描けたので、つい「タロウ君、すごいね!みんなで拍手しよう!」と言ってしまったんです。するとタロウ君は顔を真っ赤にして、部屋の隅っこに逃げ込んでしまいました。
「あれ?褒めたのに…」と思いましたが、タロウ君は注目されるのが苦手だったんですね。これは私のミスでした。でも、このミスから学べることがたくさんあるんです。
特性を持つお子さんの中には、タロウ君のように注目されるのが苦手な子がいます。これは、脳の認知機能の特性と関係があるんです。科学的に言うと、扁桃体という脳の部位が過敏に反応して、注目されることを脅威と感じてしまうんですね。
でも、大丈夫です。ちょっとした工夫で、お子さんとのコミュニケーションは大きく変わります。
まず、お子さんの特性を理解することが大切です。注目されるのが苦手なら、みんなの前で褒めるのではなく、静かな場所で1対1で褒めるのがいいでしょう。
次に、言葉の選び方も重要です。「すごいね」という漠然とした褒め方ではなく、「青い色をきれいに塗れたね」など、具体的に褒めると、お子さんも理解しやすいんです。
そして、非言語コミュニケーションも忘れずに。優しい笑顔や、軽く肩に触れるなど、言葉以外の方法でも気持ちは伝わります。

先日、この方法でタロウ君と接してみました。静かな部屋で「タロウ君、青い空がきれいに描けたね。空の色がよく分かるよ」と言いながら、優しく肩に手を置いてみたんです。すると、タロウ君はちょっと照れくさそうに、でも嬉しそうに笑ってくれました。
これは、タロウ君の認知特性に合わせたコミュニケーションだったからなんです。脳科学的に言うと、前頭前野という脳の部位が適度に刺激され、ポジティブな感情が生まれたんですね。
大切なのは、お子さん一人ひとりの特性を理解し、それに合わせたコミュニケーションを心がけることです。これは、ちょっとしたコツなんです。
例えば、視覚的な情報を好む子には、言葉だけでなく絵や図を使って説明するのも効果的です。聴覚的な情報を好む子には、リズムをつけて話すのもいいでしょう。
そして、何より大切なのは、お子さんの気持ちに寄り添うことです。「注目されたくない」「褒められるのが恥ずかしい」という気持ちを理解し、尊重することが、信頼関係を築く第一歩なんです。
みなさん、特性を持つお子さんとのコミュニケーションは、難しく考えすぎないでくださいね。ちょっとした工夫と、お子さんへの理解があれば、きっと素敵な関係が築けます。
くま先生からのアドバイスでした。みなさんの子育てが、もっと楽しく、もっと温かいものになりますように。それでは、またね!
コラムを読んでの感想やお子さんのことでお悩みの方へ
このコラムを読んでいかがでしたか?
特性を持つお子さんとのコミュニケーションについて、少しでもヒントになれば嬉しいです。お子さんのことで悩んでいる方、一人で抱え込まないでくださいね。「うちの子だけかな?」と思っていることも、実はみんな同じように悩んでいるかもしれません。ぜひ、このコラムを読んでの感想や、お子さんのことで気になることがあれば、お問い合わせフォームに書いてください。
私や、同じように子育てをしている他のお父さん、お母さんたちと一緒に考えていけたらいいなと思います。子育ては楽しいこともたくさんありますが、時には大変なこともありますよね。でも、みんなで支え合えば、きっと乗り越えられます。一緒に、お子さんの笑顔のために頑張りましょう!
くま先生は、いつでもみなさんの味方です。どんな小さなことでも構いません。お気軽にコメントしてくださいね。お待ちしています!
#褒め方 #注目 #扁桃体
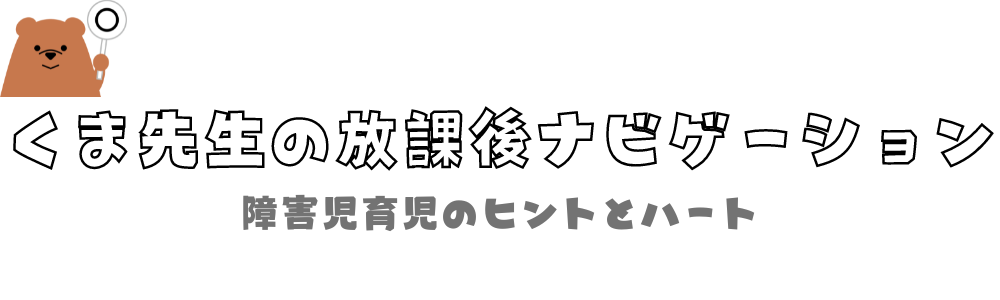



コメント