おはようございます!
ぬくぬくコミュニケーションのくま先生です。
昨日、放課後デイサービスで心温まる出来事がありました。境界知能の小学3年生のゆうくんが、初めて自分で靴紐を結べたんです。お母さんが涙ぐみながら「ゆう、すごいね!」と声をかけると、ゆうくんは照れくさそうに笑っていました。この瞬間、私は改めて「コミュニケーションの工夫」の大切さを実感しました。
みなさん、境界知能や知的ボーダーのお子さんの身辺自立、悩んでいませんか?実は、ちょっとしたコミュニケーションの工夫で、大きく変わることがあるんです。今日は、そのコツをお話ししますね。
まず、お子さんの認知機能について理解することが大切です。境界知能のお子さんは、情報処理速度や作業記憶に課題があることが多いんです。つまり、複雑な指示を一度に理解したり、長い時間集中し続けたりするのが苦手なんですね。
でも、大丈夫。ここで「コミュニケーションの工夫」が効果を発揮します。具体的には、次の3つのポイントを意識してみてください。
- 短く、具体的に伝える
- 視覚的サポートを活用する
- ポジティブな声かけを心がける
1つずつ詳しく見ていきましょう。
まず、「短く、具体的に伝える」ことです。先日、てつやくんのお母さんが「てつや、お片付けして」と言っても動かなかったのが、「てつや、赤い車を箱に入れて」と具体的に伝えたら、すぐに行動できたんです。これは、作業記憶の特性を考慮した声かけなんですよ。
次に、「視覚的サポートを活用する」ことです。言葉だけでなく、絵や写真を使うと理解が深まります。ゆうくんの靴紐結びも、実は紐結びの手順を絵で示したカードを使っていたんです。これは、視覚的な情報処理が得意な子が多いという特性を活かしているんですね。
最後に、「ポジティブな声かけを心がける」ことです。「だめ」「できない」ではなく、「できたね」「頑張ったね」と肯定的に伝えましょう。これは、自己肯定感を高め、新しいことにチャレンジする意欲を育てます。
ここで、ちょっと科学的な話をしますね。実は、ポジティブな声かけは脳内のドーパミンという物質の分泌を促すんです。ドーパミンは、やる気や集中力を高める効果があります。つまり、「できたね」という声かけは、次の挑戦への原動力になるんですよ。

さて、これらのコツを踏まえて、日常生活での声かけを考えてみましょう。例えば、歯磨きの場面。「歯を磨いて」ではなく、「前歯を10回磨こうね」と具体的に。そして、歯磨きの手順を示した絵カードを用意する。できたら「上手に磨けたね」とポジティブに伝える。
このように、ちょっとした工夫で、お子さんの理解や行動が大きく変わることがあるんです。もちろん、すぐに劇的な変化が起こるわけではありません。でも、毎日少しずつ積み重ねていくことで、必ず成長は見えてきます。
最後に、大切なことを一つ。お母さんたち自身も、自分を褒めてあげてくださいね。「今日も頑張ったな」って。なぜなら、お母さんたちこそ、わが子の最高の応援団なんですから。
くまのように大きな愛情で、お子さんを包み込んでいきましょう。一緒に、ゆっくりでも着実に、成長の喜びを分かち合っていけたらいいですね!
くま先生からのお願い
みなさん、いかがでしたか?
このコラムを読んで、新しい発見や気づきはありましたか?
くま先生は、みなさんのお子さんの成長を心から応援しています。日々の子育ての中で、うまくいかないことや悩みごとがあれば、ぜひ教えてくださいね。「こんな時はどうしたらいいの?」「この声かけ、合っているかな?」など、どんな小さなことでも構いません。みなさんからのご感想やご相談をお待ちしています。一緒に、お子さんの素敵な未来を築いていきましょう。
くま先生との対話を通じて、新しい子育てのヒントが見つかるかもしれません。ぜひ、お問い合わせフォームからご連絡ください。温かい笑顔で、くま先生がお返事させていただきます。一緒に、子育ての喜びを分かち合いましょう!
#自立 #具体的 #ポジティブ
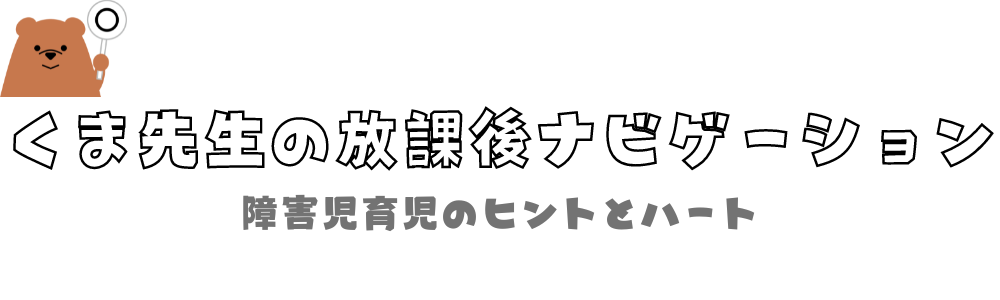



コメント