おはようごさいます!
ぬくぬくコミュニケーションのくま先生です。
昨日、放課後デイサービスで素晴らしい出来事がありました。
優先順位をつけるのが苦手なAくん(8歳)が、宿題と好きなゲームの間で迷っていたんです。「くま先生、どっちからやればいいの?」と聞かれて、ふと思いついたアイデアがありました。
「Aくん、ちょっと実験してみない?」と声をかけると、Aくんは興味津々な顔で近づいてきました。
私は2枚の紙を用意して、「宿題」と「ゲーム」と書きました。そして、「Aくん、これを大事な順に並べてみて」とお願いしました。
最初は戸惑っていたAくんですが、しばらく考えた後、「宿題」を先に置きました。「よく考えたね。どうしてそう並べたの?」と聞くと、「宿題終わらないと明日困るから…」と答えてくれました。
この小さな成功体験が、Aくんの自信につながったんです。
みなさん、優先順位をつけるのが苦手なお子さんへの対応に悩んでいませんか?実は、この「優先順位づけ」の難しさには、認知機能の特性が関係しているんです。
発達障害のあるお子さん、特に注意欠如多動性障害(ADHD)の特性がある場合、実行機能の一部である「プランニング能力」や「時間管理能力」に課題があることがあります。これらの能力は、優先順位をつける際に重要な役割を果たします。
でも、大丈夫です!ちょっとした工夫で、お子さんの認知特性に合わせたサポートができるんですよ。

まず大切なのは、視覚的な手がかりを活用することです。先ほどの事例のように、やるべきことを紙に書いて並べ替えるという方法は、抽象的な概念を具体化し、視覚的に捉えやすくする効果があります。
次に、選択肢を限定することも有効です。たくさんの選択肢があると、比較や判断が難しくなります。2つか3つの選択肢に絞ることで、お子さんの認知負荷を軽減できます。
そして、決定プロセスを言語化してもらうことも大切です。「なぜそう考えたの?」と聞くことで、お子さんは自分の思考を整理し、言葉にする練習ができます。これは、メタ認知能力(自分の思考を客観的に捉える能力)の向上にもつながります。
最後に、成功体験を積み重ねることが重要です。小さな成功でも、しっかり褒めてあげましょう。「よく考えたね」「いい判断だったよ」といった言葉かけは、お子さんの自己効力感を高めます。
こうしたちょっとしたコミュニケーションの工夫が、お子さんの認知機能の発達を促し、優先順位づけの能力を向上させていくんです。
みなさん、焦らずゆっくりと、お子さんのペースに合わせて取り組んでいきましょう。一緒に、お子さんの「できた!」という瞬間を見つけていきませんか?
くま先生は、これからもみなさんとお子さんを温かく見守り、サポートしていきます。困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。一緒に、お子さんの輝く未来を作っていきましょう!
みなさんの声をお聞かせください!
今回のコラムはいかがでしたか?みなさんのお子さんの様子を思い浮かべながら読んでいただけたら嬉しいです。
「うちの子にも似たようなことがあるわ」「この方法、試してみようかな」など、どんな感想でも大歓迎です。みなさんの声を聞かせていただけると、とても励みになります。
また、お子さんのことで気になることや悩みごとがあれば、ぜひお聞かせください。「こんな時はどうしたらいいの?」「これって普通なの?」など、些細なことでも構いません。くま先生と一緒に、お子さんの成長を見守り、サポートしていきましょう。
みなさんからのメッセージ、心よりお待ちしています!
#優先順位 #具体化 #言語化
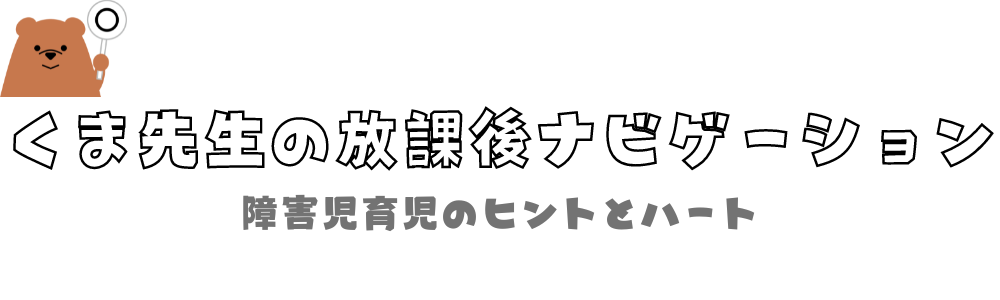



コメント