おはようございます!
ぬくぬくコミュニケーションのくま先生です。
昨日、放課後デイサービスで素敵な出来事がありました。いつもは集団活動が苦手なAくんが、みんなと一緒にゲームを楽しむことができたんです。どうしてそんなことが起きたのか、今日はみなさんにお話ししたいと思います。
Aくんは自閉スペクトラム症の特性があり、普段は他の子どもたちとの関わりを避けがちでした。でも、昨日は違いました。なぜでしょうか?実は、私たちスタッフが「コミュニケーションの工夫」をしたからなんです。
特性を持つお子さんたちは、時として周りの人とうまくコミュニケーションが取れず、孤立してしまうことがあります。これが長く続くと、自尊心の低下や不安、うつなどの二次障害につながる可能性があるんです。だからこそ、私たちは早い段階から適切な支援をする必要があります。
さて、ここで大切なのが「認知機能」との関連性です。認知機能とは、情報を処理し、理解し、記憶する能力のことです。特性を持つお子さんの中には、この認知機能に偏りがある場合があります。例えば、視覚情報の処理が得意な子もいれば、聴覚情報の処理が苦手な子もいます。
Aくんの場合、聴覚情報の処理が苦手でした。そこで私たちは、視覚的な手がかりを多く取り入れることにしたんです。ゲームのルールを説明する際、言葉だけでなく、絵や図を使って視覚的に示しました。また、ゲームの進行状況も、ボードに書いて視覚化しました。
これらの工夫により、Aくんはゲームの流れを理解しやすくなり、他の子どもたちと一緒に楽しむことができたんです。ちょっとした工夫で、こんなに大きな変化が起きるんですよ。

みなさん、お子さんとコミュニケーションを取る際、どんな方法を使っていますか?言葉だけでなく、絵や身振り手振りを交えてみるのも良いかもしれません。また、お子さんの得意な感覚(視覚、聴覚、触覚など)を活かしたコミュニケーション方法を見つけるのも効果的です。
最近の研究では、マルチモーダルなコミュニケーション(複数の感覚を使ったコミュニケーション)が、特性を持つお子さんの理解を促進することが分かっています。例えば、言葉と絵を組み合わせたり、音と動きを連動させたりすることで、情報の処理がスムーズになるんです。
大切なのは、お子さん一人ひとりの特性を理解し、その子に合ったコミュニケーション方法を見つけることです。それは、簡単なことではないかもしれません。でも、ちょっとしたコツをつかむだけで、大きな変化が起こる可能性があるんです。
みなさん、今日からできることはたくさんあります。お子さんの好きなキャラクターを使って説明してみたり、時間の経過を視覚的に示してみたり。小さな工夫の積み重ねが、お子さんの成長につながっていくんです。
最後に、忘れないでほしいことがあります。それは、お子さんの「できた!」を一緒に喜ぶことです。小さな成功体験の積み重ねが、お子さんの自信につながり、二次障害の予防にもなるんです。
みなさん、一緒にがんばりましょう。お子さんの笑顔のために、今日もくま先生は頑張ります!
くま先生からのメッセージ
みなさん、いかがでしたか?このコラムを読んで、新しい発見や気づきはありましたか?
くま先生は、みなさんのお子さんの成長を心から応援しています。コラムを読んでの感想や、お子さんについての悩み、ご質問などがありましたら、ぜひお聞かせください。みなさんからのメッセージを楽しみにしています。一緒に、お子さんの笑顔を守っていきましょう。
くま先生は、これからもみなさんの味方です。お子さんとの日々の生活で困ったことがあれば、いつでもご相談ください。みなさんの声を聞かせてくださると、とてもうれしいです。次回のコラムもお楽しみに!くま先生からの温かいアドバイスと、役立つ情報をお届けしていきますね。
それでは、また会える日を楽しみにしています。がんばりましょう!
#二次障害 #認知機能 #情報処理
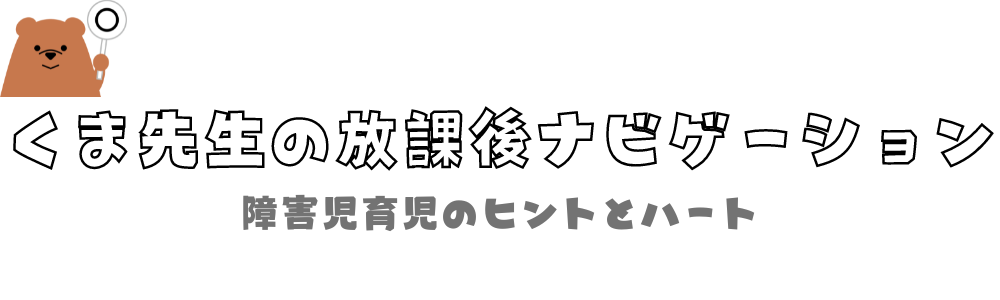



コメント