おはようございます!
ぬくぬくコミュニケーションのくま先生です。
昨日、放課後デイサービスで面白い出来事がありました。発達障害のある小学3年生の太郎くんと、その弟の1年生の次郎くんが来ていたんです。いつものように兄弟げんかが始まりそうになったとき、ふと思いついたコミュニケーションの工夫で、見事に仲直りできたんですよ。今日はその話を中心に、特性を持つお子さんの兄弟げんかを減らすコツをお話ししますね。
兄弟げんかの裏にある認知の特性
まず、太郎くんと次郎くんのけんかの様子を見ていて気づいたことがあります。太郎くんは自閉症スペクトラムの特性があり、弟の気持ちを読み取るのが苦手。一方、次郎くんはADHDの傾向があり、兄の言動にすぐに反応してしまうんです。
実は、この兄弟の行動には科学的な裏付けがあるんですよ。自閉症スペクトラムの方は、前頭前野という脳の部位の働きが少し特殊で、他人の気持ちを推測する「心の理論」という能力が発達しにくいことがわかっています。一方、ADHDの方は、前頭前野の別の部分、特に実行機能に関わる領域の活動が低下しているため、衝動性のコントロールが難しいんです。
コミュニケーションの工夫で変わる兄弟関係
さて、昨日の出来事。太郎くんが次郎くんのおもちゃを取ってしまい、けんかが始まりそうになりました。そこで私は、こんな風に声をかけてみたんです。
「太郎くん、次郎くんの顔を見てごらん。どんな表情かな?」
「次郎くん、お兄ちゃんはどうしてそうしたと思う?」
すると不思議なことに、二人とも少し落ち着いて考え始めたんです。太郎くんは弟の悲しそうな表情に気づき、次郎くんは兄が自分のおもちゃで遊びたかったんだと理解できたんですよ。
この方法が効果的だった理由は、お互いの視点に立つきっかけを与えたからなんです。特に太郎くんのような自閉症スペクトラムの特性がある子には、具体的に相手の表情や行動に注目するよう促すことで、相手の気持ちを考えるトレーニングになります。

日常生活でできる兄弟げんか対策
このような工夫は、ご家庭でも簡単に取り入れられますよ。例えば、
- 「相手の気持ちを言葉にしてみよう」ゲーム
- 感情カードを使って、今の気持ちを表現する練習
- ロールプレイで、お互いの立場を経験してみる
これらの活動は、楽しみながら相手の気持ちを考える習慣をつけられます。特に、前頭前野の発達を促すことにもつながるんですよ。
最後に
皆さん、いかがでしたか?ちょっとしたコミュニケーションの工夫で、兄弟関係が大きく変わることがありますね。特性を持つお子さんたちの認知の特徴を理解し、それに合わせたアプローチをすることで、より良い関係づくりができるんです。
くま先生に相談してみませんか?
お子さんの兄弟げんかでお悩みの方、ぜひ一度ご相談ください。お子さんの特性に合わせた具体的なアドバイスをさせていただきます。一緒に、笑顔あふれる家族関係づくりを目指しましょう!
#兄弟げんか #相手の気持ち #コミュニケーション
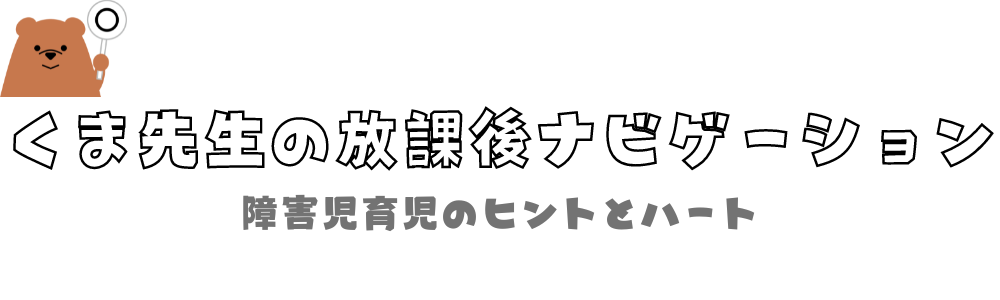


コメント